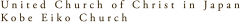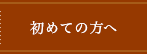4月5日(日) 棕梠の主日礼拝説教「尋問」
更新日: 2020.04.14
受難節第6主日/棕梠の主日(2020.4.5)礼拝説教
創世記22章6-14節,ヨハネによる福音書18章28-40節 牧師 野田和人
牧会祈祷
憐れみと慈しみに富みたもう、私たちの復活と命の主イエス・キリストの父なる神さま、私たちの愛するこの日本の地においては新しい年度の初め、教会の暦においては受難節第6主日/棕梠の主日にあって、あなたに信頼をよせるすべての民とともにこの礼拝へと招かれている恵みを心より感謝いたします。
けれども神さま、私たちが生きているこの世界では、新型コロナウイルスのパンデミックによって計り知れないほどの人々が、痛み、悲しみ、不安と困難の中にいます。また、不正と抑圧、暴力の連鎖も続いている中で、「御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ」と祈る私たちは苦しんでいます。神さま、この世界は兄弟を守る者となることを拒んだ多くの「カイン」で満ちています。主よ、あなたの十字架はあまりにも冷たく素朴です。
けれども主よ、あなたはその十字架を通して、ご自分がどこまでも私たちを赦し、私たちの拒絶を受け止め、私たちの苦しみを共に担おうとされる方であることを、十字架のあたたかさと豊かさを、私たちに示してくださったのだと私たちは信じています。
私たちが、あなたが共に担ってくださる苦しみに備える中で、あなたが私たちに賜る良いものを見出すことができますよう、私たちにあなたの御心に触れさせてください。
悲しみと憤りを治めてくださる神さま、失われていった数多くの大切な命を私たちが心に刻み、私たちを生かしてくださるあなたへの信頼と復活の主に相まみえる希望のうちに、贖いの主に従う道を進ませてください。
最も小さいもののためになしてくださる私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
説 教 「尋 問」
ヨハネによる福音書の18章と19章には、「ホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように、イスラエルの王に。」(ヨハネ12:13)との歓呼の声に満ちたエルサレム入城から始まるイエスさまのご受難の中心部分、イエスさまの逮捕から始まって、ユダヤ人による裁判(尋問)、ローマ人であるピラトによる尋問、それに続くイエスさまの十字架刑と死、そして埋葬についてが記されています。ちょうど使徒信条にある「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ」のところです。今日与えられたテキスト(聖書箇所)は、こうした流れの内の、ピラトによるイエスさまに対する最初の尋問の場面、ピラトがイエスさまとユダヤ人たちとの間で一人右往左往しながらユダヤ人の訴えに屈する場面が描かれています。
ところで、この福音書が書かれた意図、その目的は、結びの20:31にもはっきりと記されているように、「あなたがたが、イエスは神の子キリストであると信じるためであり、また、あなたがたが信じてイエスの御名によって命を得るためである」となっています。ですからイエスさまの受難物語も、それを聞かされ、また読む者が、神の子キリストであるイエス、神と等しい者(5:18)であられるイエスさまを信じる信仰に毅然として留まることができるために記されたということになります。そのような主イエスへの信仰の決断が、この福音書を読む者すべてに、当時のユダヤ人たちや現在の私たちにも迫られているわけです。一体どのような信仰の決断が迫られているのでしょうか。
今日のテキストのポイントは、まず31節と32節にあります。「ピラトが『あなたたちが引き取って、自分たちの律法に従って裁け』と言うと、ユダヤ人たちは、『わたしたちには、人を死刑にする権限がありません』と言った。それは、御自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。」そうなのです。使徒信条にあるように、「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ」たのではなく、確かにイエスさまは苦しみを受け、十字架につけられたのですが、そのような受け身の意味ではなくて、主イエス自らが苦しみを負い、イエスさまご自身が自ら十字架を選び取られた。罪のない方が罪人に代わって、罪人の一人として十字架を担われた。このことを、このイエスを信じることを福音書記者は私たちに迫っているのではないでしょうか。
今日のテキストの中心部分、ピラトとイエス、ピラトとユダヤ人たちとの間のやり取りも、イエスに対して一見好意的でイエスの擁護者のように見えるピラトの仲介的な役割、イエスとユダヤ人両者の間を、ローマのユダヤ総督として何とかうまく治めようと苦心するピラトの姿にポイントがあるように見えますが、読み進めるうちにやはり中心は、総督官邸の中にいてじっと動かないイエスさまにあるのだということが分かってきます。
場面は、過越の祭りの警備のためにエルサレムにあるローマ総督官邸にいたピラトのもとに、ユダヤ人たちがイエスを朝早く連れて来るところから始まります。彼らが官邸に入らなかったのは、自分たちの清さを守るためでしたが、そのようなユダヤ人たちの身勝手な振舞にもかかわらず、それならということで、物分かりの良さを示すかのように、ピラトの方からユダヤ人たちの前に出て来ます。そして、お前たちの魂胆は分かっているぞとばかりに、政治的な問題ではなく宗教的な問題なら、自分たちの律法に従って裁けと突き返すのです。しかしユダヤ人たちは、すでに死刑判決は下していてもその執行権がないということで、ユダヤ式処刑である石打ち刑ではなく、暴徒らに対するローマ独自の処刑である十字架刑に固執します。そしてこの後に鍵となる言葉が挿入され、福音書記者の意図が示されるのです。
「それは、御自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった」。実はすでに12:33にも同様な言葉があり、この箇所の伏線となっています。先週の聖書箇所です。「イエスは、御自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、こう言われたのである」。どう言われたのかというと、「わたしは地上から上げられるとき(これは十字架に上げられることと神によって天に高く挙げられることの二つを意味しています)、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう」。
ユダヤ人たちがあくまでもローマの十字架刑に固執したのは、またピラトが結局イエスさまを十字架につけるためにユダヤ人たちに引き渡したのは、彼らがそう望み、彼がそうせざるを得なかったからではなくて、イエスさまご自身がそれを選び取られたからということ、その預言が成就するためにはどうしても十字架が必要だったからというわけです。
このことを示した後、ピラトとイエスさまとのやり取りが描かれていきます。ピラトの尋問は四つ。「お前がユダヤ人の王なのか」、「一体何をしたのか」、「それではやはり王なのか」、そして「真理とは何か」です。これらはすべて見事に「この世」を基準にした尋問となっています。
「ユダヤ人の王、すなわち政治的な意味でローマ皇帝への反逆者なのか」。イエスさまの「そうではない」という答えを期待していたピラトに対して、イエスさまは彼には思いも寄らない問いを返します。「自分の考えでそう言うのか」と。ピラトの主体性を問うのです。ピラトはまさかそんな問いが返ってくるとは思っていませんでしたから、あわててしまって、とにかくこの問題をできるだけ早く片付けたくて、「私の問題ではなくお前たちの問題なのだから、難しいことは言わずに何をしたのかだけを言いなさい」と命じます。するとイエスさまはまたしても直接には答えず、「わたしの国は、この世には属していない、この世からのものではない」という、いわば神学的な受け答えをします。これは、「わたしの国はこの世の政治的なものではないから、あなたが心配するには及ばない」ということではなく、「わたしの国」というのは「神の国」であるということ(3:3,5)、そして私の王としての支配は、上なる神の領域に属しているということを表すものです。
ピラトはそこであまりよく分からないままに、「やはり王なのか」という曖昧な問いしか返せません。王は王でも、イエスがこの世の政治的なユダヤ人の王ではなく、神の国の、イスラエルの王であるということは理解できません。
「その王が真理について証しをするためにこの世に来たのだ。真理に属する人は皆、わたしの声を聞く。羊は羊飼いの声を聞き分ける」。
しかしこの世の羊は羊飼いの声を聞き分けませんでした。そして羊飼いの声を聞き分けなかった者の最後の尋問が「真理とは何か」です。ピラトのお手上げ状態が目に見えます。これに対する答えはありません。記されていません。受難週の初め、私たちはどう答えるのでしょうか。「真理とは何か」、答えはすでに示されていますね。
ピラトは、気にかかっていたとは思いますがイエスさまの答えは聞かずに、この後、総督官邸の外にいるユダヤ人たちの前に出て、ローマのユダヤ総督としてイエスさまの無罪を宣言します。そしてその後、彼の予想に反して「その男ではない。バラバを」との声を聞くことになるのです。
ピラトの物語はもう少し続きますが、福音書記者がここで私たちに示したいことは、ピラトという人物を通して主イエスの真実な姿を明らかにしていく中で、真理について証しをするためにこの世に来られたイエスさまに、この世がどのように敵対しているかということだと思います。ピラトも、官邸の外で待っている、自分たちは清いと思っているユダヤ人たちも、そして私たちも含めたこの世が、いかに神さまに敵対しているかということです。そしてそのように神さまに敵対しているこの世が、イエスの国、神の国と一つになるためには、イエスご自身が十字架を選び取ること以外に方法がなかったということ、他のいかなる仕方でもなくこの方法しかなかったということを福音書記者は最も伝えたかったのではないでしょうか。そう。“No Cross, No Crown.”「十字架なくして王冠なし」。“No Cross, No Crown.”ここに真理があります。
受難週の初め、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためにただ一度十字架を担われ、その羊のために命を捨てられた主イエスを心から想うとき、「その男ではない。バラバを」と私たちが再び叫ぶことはできないのです。祈りましょう。
神さま、主の年2020年の受難週の始まりの朝、この週、ゴルゴタへの道を十字架を負って進まれる主イエスの姿から私たちが目をそらすことなく、その苦しみが何のためであったのかを、今この時、それぞれの場で祈りを合わせているお一人おひとりと共に、あらためて私たちに分からせてください。「主の山に備え」があることを、受難週洗足木曜日礼拝、受難日正午礼拝を通して私たちに示し、復活の朝の希望の光の中へと、どの私たちをも導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。